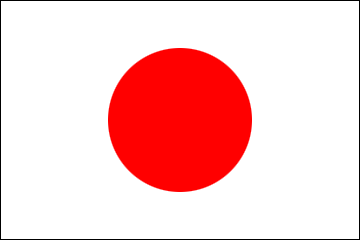フランスと日本の親権制度の相違点について
- 近年の人的・物的国際交流の進展に伴い,外国に移住しそこで外国人と国際結婚して家庭を築かれる方々が増加しています。
- 日本とフランスの間も同様の状況であり,当館領事窓口にはフランス人との結婚の届出や出生届出のため,御来館なされる方がたくさんいらっしゃいます。
- その一方で,これら国際結婚された一部の方々には不幸にして結婚生活が破綻してしまい,一方の親が他方の親に無断で子供を国外に連れ出す,いわゆる「国際的な親による子の奪取」等の親権行使に関する問題が報告されています。
- フランス政府はこのような問題の発生について,東アジア諸国の中で日本人が関わる事例が最も多くなっていることを指摘し,また,「日本の親による子の奪取」の事例では,具体的な解決策を見出せないものが多く発生していることを憂慮し,政府として真剣に取り組む意向を示しています。
- 国際結婚をされた方の中には,様々な理由を原因として,外国での結婚生活が困難となり,離婚の問題や,子供の養育についてどのように対処するのかといった問題が発生する場合があります。フランスでは一方の親の同意を得ることなく,他方の親が国外に子供を連れ去ることは刑罰の対象となります。さらに,連れ去り行為は,子供にも大きな影響を与えることとなります。
- ついてはフランスに居住される皆様に,親権についてのフランスと日本の制度の相違点について以下のとおり取りまとめましたので,参考としていただければ幸いです。
- また,外務省(日本の中央当局)では,ハーグ条約に基づく返還援助申請及び面会交流援助申請の受付・審査や当事者間の連絡の仲介,外務省の費用負担による裁判外紛争解決手続(ADR)機関の紹介,弁護士紹介制度の案内,面会交流支援機関の紹介等の支援を行っています。詳しくは下記のページを御参照ください。
- ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
 (※外務省のホームページが開きます。)
(※外務省のホームページが開きます。)
フランスと日本の制度の相違点
1.離婚・離別後の親権
フランスにおいては、両親が結婚していても、民事連帯契約(P.A.C.S.)の関係にあっても、また、事実婚の関係にあっても(子供に対する認知があれば)、親権は両親が行使するのであり、離婚や別離があっても、原則として共同親権のままであり(民法典第373-2条)、両親と子供との関係は維持され、両親は互いに他方の親と子供との関係を尊重しなければなりません。
この点、日本では、両親が結婚関係を継続している間は、親権は共同で行使されますが、離婚後は、共同親権が認められておらず、一方の親が親権者となるのであり(単独親権、民法第819条第1項)、フランスの制度と大きく異なっています。
2.離婚・離別後の親権の行使
このように、フランスでは、共同親権が維持されますから、離婚・離別後に、子供と生活を共にしない方の親と子供との関係は、「親権の行使」という観点から重視されます。
日本においては、離婚後に、親権を行使しない親の、同居しない子供との面会は、民法に明文の規定はありませんが、判例上認められています(面接交渉権)。日本では、面接交渉権は、子供の健全な成長という観点から認められていますが、フランスでは、親権の行使のための親の当然の権利という色彩が強いことに注意を払う必要があります。
例えば、子供と同居しない親は、当然相手(子供と同居する親)の居住地を知る必要があります。従って、子供と同居する親が住居を変更する場合は、変更後の居住地を、他方の親に告知することが義務付けられています。住居変更について折り合いがつかない場合は、裁判所が調整を行うことになります。変更の通知は、民事上の義務にとどまらず、離婚・離別後、未成年の子供と同居する親が、住居変更を他の親に伝えない場合は、親権行使を侵害したとして、刑事罰(6ヵ月以下の拘禁刑又は7,500ユーロ以下の罰金)を科される可能性があります(刑法典第227-6条)ので、注意が必要です。
3.いわゆる子供の連去りの問題
フランスでは結婚中又は同居中、一方の親が他方の親に無断で子供を連れ去る行為は、やはり親権行使の侵害に当たるとして犯罪とされており、1年以下の拘禁刑又は1万5,000ユーロ以下の罰金に処せられる可能性があります(刑法典第227-7条)。夫婦間の折り合いが悪くなった場合に、父又は母が、他の親の承諾を得ることなく子供を連れ去って、別のところで子供と生活を始めた場合、子供の連れ去りが暴力等を伴うことなく平穏に行われたとしても、他の親の親権行使を侵害する犯罪であるとみなされます。